
泉大津市文化協会のキャッチフレーズは 「文化協会で広がる四つのチャンス」がですが、四つのチャンス とは「教養の場」「創造の場」「親睦の場」「発表の場」です。
現在文化協会には事業部会が5部会と専門部会が18部会あり、 多彩な活動をしていてます。ここにその活動と記録を配信します。皆さんも文化協会という大きな輪の中に入って楽しく自己の能力を発揮し有効的に時間を使って下さい。
文化協会の会員数は410人で、専門部会が18部会あり、それぞれの部会では活発な活動をしています。ここに活動記録を配信しますが、皆さんも何れかの専門部会に所属して能力を発揮してみませんか。もし入りたい部会がない場合は「所属なし」で入会することもできますし、仕事や活動の場が 泉大津市内の方も文化協会に入会できます。 入会すると「文化協会だより」(年3回)や「社会見学会の申し込書」「会員作品展の出品申込書」「歴史探訪案内」など資料をお手元に郵送させていただきます。入会すると全ての事業に参加できます。通常は4月の入会になりますが、途中からでも入会できますので入会ご希望の方は「入会のご案内」をご覧下さい。
文化協会の部会
1. 演芸演劇鑑賞部
2. 絵画部
3. コーラス部
4. 茶華道部
5. 詩吟部
6.写真部
7.シャンソン部
8.書部
9.川柳部
10.箏曲部
11.短歌部
12.陶芸部
13.日本舞踊部
14.俳句部
15.民踊部
16.フラメンコクラブ
17.七宝焼きクラブ
18.ワンストロークペインティングクラブ
1.演芸演劇鑑賞部
当部は、平成18年に結成しました。お笑いをキーワードに鑑賞活動をしています。お笑いは「笑う門には福(健康)来る」と言われ、これらを踏まえ演芸演劇鑑賞部では、落語を主に講談、大衆演劇等を天満天神繁昌亭や神戸・喜楽館、浪切ホール等で鑑賞しています。
鑑賞部では会員を募集しています。落語等に興味のある方は歓迎します。(会費は月200円/年2,400円です。)
2.絵画部
クロッキー会にも参加してください
泉大津市教育支援センター(旧戎小学校)で毎月・第2週の木曜日夜、午後7時〜9時にクロッキー(デッサン)会を行っています。
3.コーラス部
泉大津市合唱連盟
平成24年に4団体が増え現在は8団体。隔年に開催する交歓演奏会や他の年にも合唱に関連した行事を行い、人と人との絆を大切にして合唱をより楽しく広げて行きたいと思っています。
少年少女合唱団 月4回土・日曜の午前に幼稚園から中学2年までの子ども達が青少年ホームで練習しています。
混声合唱団 毎週土曜日、13:30より勤労青少年ホームで練習。年齢は20代〜80代と幅広く男声6名と女声22名が宗教曲・ポップス・民謡等を練習。
穴師コーラス 練習は水曜日に勤労青少年ホーム。
女声コーラスあじさい 日本の心と言葉を大切にして誰もが親しめる歌を練習。月3回・月曜の朝からの練習と後の食事会も楽しみとなっています。
愛唱歌クラブ「カトレア」 誰もが知っている童謡・愛唱歌など日本の美しい歌を楽しく歌う事を通して仲間づくりや健康な人生を送りたいと願っています。
女声コーラス「ペペロッソ」 企業や専門職で働く人や子育て真っ最中の人、現役の学生など20代〜50代の多忙なメンバーですが、月に2回レッスン。あすとホールで開催されるイベント等にも参加しています。
条南若葉会 平成24年に結成した、 条南町老人会(長生会)が母体の平均年齢83歳のコーラスグループ。
歌クラブ「ヴィオレッテ」 総合福祉センターのクラブとして平成22年に発足。浜街道まつりで狂言と共演をするなど生き生きと楽しく活動しています。
混声合唱団では団員を募集
<練習日>
毎週土曜日、13:30~16:30
<場 所>
勤労青少年ホーム
<講 師>
中村 真貴子(指揮・指導)
柳原 愛友美・山崎 有希(伴奏)
入会ご希望の方は、練習を見学してください。
4.茶華道部
昭和17年泉大津市制施行の年に泉大津市茶華道連合会が結成されました。それから数年後、茶華道連合会は他の文化団体と共に、文化協会の設立に参加。現在茶華道部の大半が泉大津市茶華道連合会に所属し、子どもたちに伝統文化の心を伝承するために泉大津市内の幼稚園・保育園・認定こども園・小学校への出前講座に出向き、子どもたちと楽しみながら地域の中で活動しています。
5.詩吟部
詩吟部がいつから文化協会に名を連ねたかは分かりませんが、現在詩吟部というのは、母体は泉大津市詩吟連盟であります。詩吟連盟は昭和47年に泉大津市内に教室を持つ詩吟の多くの流会派の連携で結成されたました。現在詩吟連盟は6つの流会派が所属し、会員は100名ほどとなっております。文化協会は個人登録制であることから、各会派の代表、有志が登録しております。詩吟連盟は毎年春に研修会、秋に文化祭参加の吟詠大会を主たる行事として開催しております。個々には公民館、福祉ボランティアなどの分野でも活動しております。
詩吟連盟詩吟大会
泉大津市詩吟連盟が一同に会して盛大な詩吟大会が行われました。体と知力のバランスがあってこそ、これからも健やかに吟じ続けられ会の発展をお祈りします。

6.写真部
「泉大津写真クラブ」として平成18年に結成。偶数月の第1金曜日に北公民館で例会を行っています。例会では各自が撮影したA4判の作品を黒板に掲示し合評します。また、バスをチャーターして桜や紅葉の名所などを選んで撮影会を実施し、作品展も会場を変えて開催しています。写真に興味のある方募集中です。
7.シャンソン部
シャンソン部は平成23年に結成。泉大津市の文化祭では「秋に唄う人生のドラマ、シャンソン」で参加。唄う事が大好きで、人生を美しく、楽しみ、声を出して、甘い恋歌・コミカルな歌・美しい歌・人生の歌などフランス語圏の古き良き時代の歌話であるシャンソンを、日本語で、一人ひとりの個性を生かし自分の歌にして唄います。皆さん、仕事に家事にと忙しい中、仲間との語らいの楽しみも大切に「人生の良き思い出」のページ作りに歌い練習しています。
8.書部
文化協会会員作品展や市展に出品し、書に関係のあるところを見学するバスツアーもしています。「書」の世界は本当に幅広く奥深いものです。どの部門をとっても同じことが言えると思えますが、高い山に登ることと同じで、いろいろな登り道があり、息苦しいぐらい困難な時もありますが、途中ほっとする時もあります。書部への入会を歓迎します。
書部が第2回篆刻教室 開催
8月10日おずぷらざ(テクスピア5階)で篆刻教室を開催しました。指導は書部会員の奥村章氏(条東地区)で9名が参加し、それぞれ世界で1つしかない自分の印を制作しました。 書部としての活動として定例化していこうと張り切っています。書に興味ある方、文化協会に入会してみませんか?

9.川柳部
川柳部は平成29年結成。毎月第2水曜日13:30から、川柳の集まりを勤労青少年ホームで行っています。川柳は、5・7・5のたった17文字で人間の可笑しみや哀しさや、はたまた愚かさなどを表現します。季語もなく、取り組みやすいと思われがちですが、なんと奥は深く、また言葉の魔法によって何気ない日常を愉快なものに変えてしまいます。毎月の部会の様子は、皆さんから投句された宿題を読み上げて「良いな」と思った句に挙手をします。何度挙手しても良いのですが、自分の句には挙手できません。手が多く上がった句から「天」「地」「人」と選ばれていきます。毎回の皆さんの句を記録して、その年の記念として「川柳集」の本を作って残しています。読み返しながらその成長を感じるのも良いものです。
第64号文化協会だより、「柳壇」掲載句
熱中症こわい病気に仲間入り
岩谷 チエ子
時間給上がる前に物価高
澁田 天游
ユニークと天才肌は紙一重
岩崎 久美子
「若いね」と言われる度に背筋伸び
川崎 廣進
執拗に急いだマイナぼろばかり
横田 節子
川柳部が作品集6号を発行
川柳部が昨年度の作品集を制作しました。創部6年目の作品なのでタイトルは6年に因んで「むつまじく」です。B6サイズ、69頁。
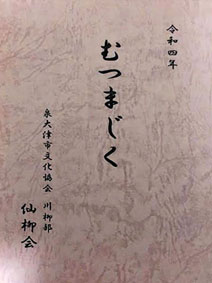
母の日川柳
2023年も、FM泉大津さん、西日本花き(株)さん、と川柳部のコラボで、「母の日川柳」を市民のみなさんに公募し、金賞、銀賞、銅賞が選ばれて、西日本花き(株)さんより花籠がプレゼントされました。
金賞
どの花も母の愛ほど咲き誇れ
祐仙 淳子
銀賞
送られて花より開く母の笑み
川崎 廣進
銅賞
母の顔笑顔になると花が咲く
みーみーさん

茶華道部とコラボ
令和4年11月26日、テクスピア大阪のホワイエで川柳部と茶華道部がコラボしました。川柳部は色紙をパネルに展示し入場者に好きな句にシールを3つ貼って頂きました。

良い夫婦の日川柳コンテスト
FMいずみおおつで公開選評
令和4年11月20日、良い夫婦の日川柳コンテストがFMいずみおおつ・西日本花き株式会社・文化協会川柳部の共同で行われました。44句の応募の中から選句された金賞、銀賞、銅賞には写真の花束が西日本花き株式会社さんから贈呈され、川柳部から金賞と銀賞の次の句が選ばれました。
〔金賞〕
お互いに花を持たせる良い夫婦
新子 美奈子
〔銀賞〕
彼岸花愛でては歩く老い二人
横田 節子

文化協会だより第61号「俳壇」掲載予定(10月1日発行予定)
お医者さん画面見ないで顔を見て
南 タカ子(宇多地区)
孫が来る用意するもの隠すもの
古垣内 求 (上條地区)
大丈夫優しいウソもあってよい
岩崎 久美子( 旭地区 )
楽しみはやっぱり箱を開けるまで
高津 徹也( 浜地区 )
夫婦でも言って良い嘘悪い嘘
山口 晴子( 高石市 )
川柳部が2つのコラボ企画
1つは川柳部とコンビニのセブンイレブン北助松店さんとのコラボで9、10月に地域の皆さまにお題「コンビニ」で川柳を募集したところ82句の楽しい川柳が集まりました。
2つめはの良い夫婦の日(11月22日)に因んだ川柳を、FMいずみおおつと西日本花き(株)、川柳部で共同企画で募集しました。なんと今回は日本全国から131句が集まり、次の3句にアレンジフラワーがプレゼントされました。
〔金 賞〕
今満開一緒にいようね枯れるまで
泉大津市 笑色
〔銀 賞〕
変わる世に変わらぬ桜夫婦愛
福島県二本松市 やんちゃん
〔銅 賞〕
コロナ花で夫婦の愛を試された
泉大津市 天久美

4冊目の作品集を発行
川柳部は発会以来5年目を迎え、メンバーも28名に増えました。1年間の各人の句をそれぞれ10句づつ集めた作品集が出来ました。題名も皆さんから公募し、4冊目なので「4」を織り込んだタイトル「四季折々」。コロナに明け暮れて、通信に切り替えたりしながら毎月会を催しています。
( 令和3年5月1日 発行 B6サイズ 69頁)
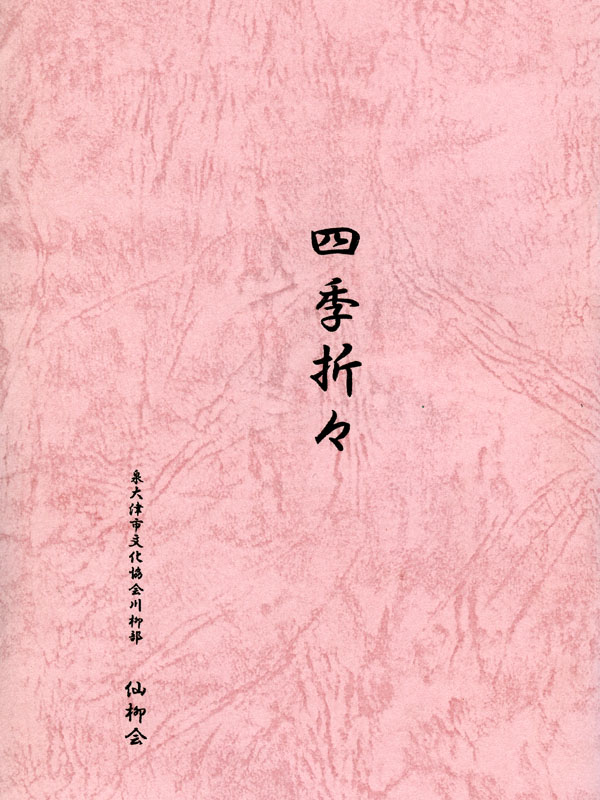
仙柳会では会員募集
<練習句会> 毎月第2水曜日、13:30~15:00
<場 所> 勤労青少年ホーム2F
<講 師> 祐仙 淳子
入会ご希望の方は句会を見学してください。
10.筝曲部
昭和33年発足し、49年より毎年秋には市の文化祭に参加。その間「泉大津市成人式」「浜街道まつり」などへの出演。また毎春の国立文楽劇場へ参加しています。
下村さんが
NHKFM「邦楽百番」に出演
邦楽部の下村弘子(菊多嘉弘子)さんが令和3年9月11日にNHKFMの「邦楽百番」に出演し、宇治巡りを演奏しました。

筝曲の会開催
令和1年11月24日、午後1時からテクスピア大阪小ホールで、泉大津市文化祭参加として開催しました。

11.短歌部
短歌・谺(こだま)は、南公民館を学習場所として昭和53年4月に発足いたしました。短歌を通じて心豊かに生活の充実をはかる事を趣旨としています。毎年発行する合同歌集は平成30年で39冊目となりました。1冊目は昭和56年「花環」と名付けられ、寺田恒子先生の発案で誕生いたしました。先生亡きあと、栃尾先生が編集に関わって下さり1冊1冊の花の名が繋がって今に至っています。また数年前より、花みずき会の方が加わり一層楽しい歌集となりました。健康に気をつけながら歌作りに楽しみ、皆と逢える喜びを味わいながら日々過ごせれば有難いことだと思っています。40年を越えて続けられている短歌会が、心の拠り所として学習の場として、これからもあり続けたいと思います。
「文化協会だより」第64号「歌壇」に掲載
衣更するたび思う又着れるだろかと老ゆ身愛しみて
舟越 タミ子
二年前骨折した日と同じ日にコロナと判りまさかのまさか
小野寺 敏子
昨夜の月見忘れて立つ朝ぼらけまんまるのまま有明の月
増本 輝身得
歌集「杜若」発行
今年の歌集は『杜若』(かきつばた)です。
いま、新型コロナウイルスの流行病はわが国だけでなく、世界中にひろがりこの疫病と戦っています。「三密」を避ける日常生活を守りながら、一刻も早い疫病の終息を願っています。
第45代聖武天皇は天皇の御代の流行った疫病を鎮める願いをもって、東大寺を建立、大仏を安置されました。
そして、宮中行事の一つとして薬狩りが行われていて、薬狩りに行く前に衣に杜若を摺りつけて出かけていました。
天皇に仕えていた大伴家持のその時の歌
杜若衣に摺りつけ大夫の着襲(きそ)ひ狩する月は来にけり(巻十七・三九二一)
杜若を衣に摺り染にして大夫たちが着飾って狩をする月がやって来たことだ
杜若は薬草であったようです。また、野の水辺をいろどるカキツバタは美しい人をも形容する花でもあったようです。
今年はこの歌の杜若を歌集名にと迷いなく定めました。一刻も早いコロナの終息を、せめて気持だけでもと祈るばかりです。
何が起こるかわからない中で私達は生きています。大きなことは出来ませんが、身のまわりで出来る佳き事を日々心掛けていこうと思っています。
「こだま会」は仲の良いクラブの伝統です。メンバーの入れかわる中にも皆仲良く会が進み、この歌集も長きにわたり発行されています。心身ともに健やかに、が願いです。皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。
令和2年10月吉日
栃尾 悦子
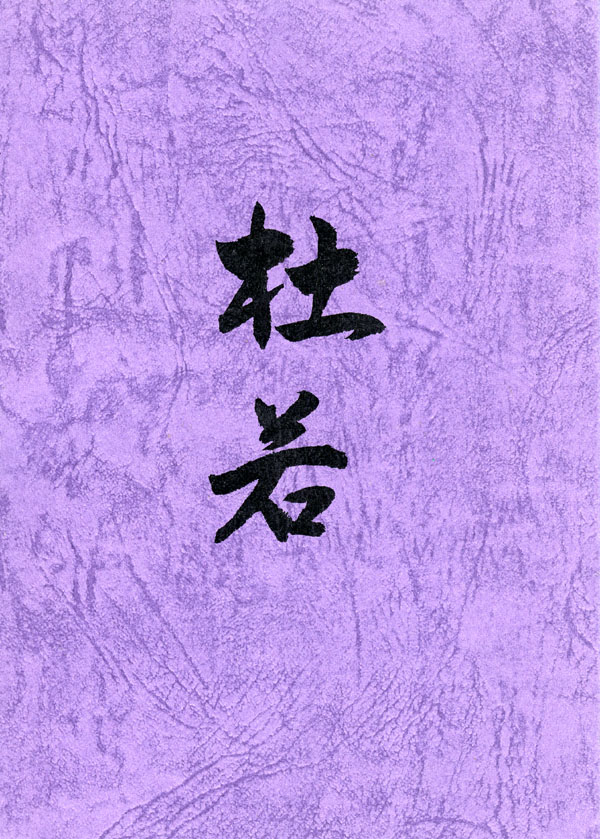
12.陶芸部
陶芸部は土を触る事による老化防止や日常生活で使用できる器などの制作と、個人個人で特徴ある作品作りに一生懸命取り組んでいます。市内では、南公民館・北公民館・個人の陶芸教室など作陶の出来る場所があり、一人でも多くの方々に作陶の楽しみを味わって欲しいものです。また展示会の見学や鑑賞会などの参加を通じて、陶芸の輪を広げ各々のレベル向上が見込まれる取り組みなどの企画が出来ればと思っています。陶芸の底辺拡大として取り組んでおります。粘土遊びを行う事により、将来につながるものと思いますので、陶芸部へ入部きたいします。
13.日本舞踊部
昭和47年、前市民会館の柿(こけら)落しに「第1回日本舞踊の会」を開催、以後文化祭を発表の場として各流派協力し、芸の向上・精進に励んでまいりました。平成18年からは新舞踊と相互協力し、日舞をより親しみ楽しんで頂こうと取り組み、皆様からもご好評を頂いています。日舞は立方(舞い手)、地方(唄・三味線・琴)、鳴物(太鼓・小鼓・笛)から構成される古典芸能の集大成です。めまぐるしく移り過ぎる昨今、それらを継承・発展させていくには、様々な事情があります。日本古来からの礼節、風習、作法、和のしつらえ、それらを育む伝統文化はじりじりと後退し、かつて日本人が誇りとした良風美俗は徐々に薄れていく様です。その中、当市には日舞をこよなく愛し、日々のお稽古に精進する愛好者が根強く定着しています。平成15年から「文化庁補助事業伝統文化親子教室」を、幼児から高校生対象に無料で開講しています。「日本の子供に…、日本の唄で…、日本の踊りを…」を主旨に、日舞を通して長幼の序を弁えた正しい言葉使い・豊かな情操・思いやる心を次代に、和服に親しむことを第1歩に基本を指導します。過去から受け継いだものを未来に繋げることが、伝統芸能に携わる者の使命だと思っています。
14.俳句部
泉大津市の俳句部会は、森本恭生師の指導の下に「栲幡(たくはた)句会」があり、また「泉大津句会」「山吹句会」と3つの句会が一丸となって「ホトトギス」誌の傘下「未央」の誌友として頑張っています。俳句は座の文学であり、一人では駄目です。座の文学ゆえに、句のみでなく、自然を愛し人を愛し極楽の時間を与えてくれます。一人でも多くの人と共に、春秋を詠み、日本人である喜びを謳歌したいと願っております。三つの句会の門は、いつでも全開しております。
「文化協会だより」第64号「歌壇」に掲載
心置く小さき草に秋の声
須谷 友美子
一句書き留めて夜長の灯消す
山上 輝子
赤い羽根帽子につけて戻りけり
中野 禎子
枯蔦や葉も実も風と共に去り
新垣 悦子
蓑虫や糸に命を預けをり
榊原 玲子
<俳壇>
病棟の消灯までの秋灯下
川上 法子(条東地区)
爽やかや湖面は天の鏡なる
小梶 綾子(浜地区)
分身の杖の見つけし竜の玉
金銅 塩子(条南地区)
秋晴や今日の一日に感謝して
北野 葉子(浜地区)
父の日や父の齢越へ父偲ぶ
奥田 不二子(条南地区)
文化協会市民俳句大会
コロナ化のため通信句会
(令和3年9月25日)
古賀 しぐれ選
〈天〉
横顔のわづかの愁ひ扇置く
旭地区 須谷 友美子
〈地〉
推敲の秋の扇の開きぐせ
浜地区 多田羅 紀子
〈人〉
蕎麦(そば)の花木霊(こだま)崇むる塗師の里
条南地区 池田 幸恵
栲幡(たくはた) 句会の幹事をされていました 森本恭生師 が令和3年6月6日に死去されました。享年79歳。
森本恭生師 に捧ぐ栲幡句会会員の弔句です。
各句会への入会歓迎します。川柳部・
15.民謡部
平成18年に民踊部が出来て文化協会所属となりました。民踊部はスローガンに「楽しく笑顔で、踊りの輪から人の和」を掲げて部会員一同踊りの練習に励んでいます。民踊研究会を始めとして、市民納涼・民踊おさらい会・民踊講習会に参加。皆さんも私たちと共に踊りの輪に入って下さい。ご参加を歓迎します。場所は、総合体育館・南公民館・北公民館・各地区長寿園・福祉センターなどです。
16.フラメンコクラブ
和泉市にて《上西恵子フラメンコ教室》が開かれています。先生の指導のもと、子どもから大人まで熱心に楽しく練習に励んでいます。
連絡先
090-3910-5280 上西恵子まで

17.七宝焼きクラブ
北公民館にて、第2第4木曜日、午前10時から12時で七宝焼クラブがあります。部員数が少ないですので増えるように願っています。

18ワンストロークペインティングクラブ
東助松町の堂下さんの自宅にて教室があります。生徒さんの都合に合わせてレッスン日を決めるそうです。わかりやすく丁寧に教えていただけます。
連絡先
090-1910-5748 堂下まで
